人間-自然関係の精神病理 その2
人間-自然関係の精神病理 その3
人間-自然関係の精神病理 その4
人間-自然関係の精神病理 その5
人間-自然関係の精神病理 その6
健忘 (Amnesia)
メツナーが次に挙げる有用な診断アナロジーは、生物種としての私たちがある種の集団的健忘症にみまわれているという考えである。私たちは、かつて祖先たちが知り、実践していたこと -ある種の心構えや知覚、人間以外の生命に共感したり、同一化する能力、神秘的なものへの敬意、自然世界の無限の複雑性との関係に対する謙虚さ- を忘れてしまっている。人間の意識の歴史における数々の決定的なターニングポイントで、私たちはある特別な発達の道を選んだため、何か他のものを忘れ、放置してしまった。
メツナーは健忘のメタファーを、ポール・シェパードの見解(「その3」を参照)に当てはめて考えている。つまり、私たちは青年期の通過儀礼を忘れ、新石器時代の狩猟採集民が持っていた謙虚さや繋がりを忘れ、自然世界内で起こるエネルギー変換の絶え間ないサイクルへの知覚感受性を忘れたのだという。デヴリュー (Paul Devereux) らは著作『Earthmind』で、健忘について次のように述べている。
私たちは長い間、かつての地球との親近性を思い出せないままでいる。この健忘のおかげで、今、私たちに押し迫ってくる環境問題は衝撃となってきている。… 実際には2重に忘れているという健忘が発現していることに気づく。文化が惑星との調和した生きかたを忘れていることと、それを忘れてしまったことをも忘れていることだ。1この健忘のメタファーをさらに深めると、「心的外傷性健忘 (traumatic amnesia)」の可能性も検討できる、とメツナーは言う。児童虐待やレイプ、戦争における戦闘、事故や自然災害などの体験が及ぼす影響についての研究から、人が全く自分ではどうすることもできない、不可抗力の状況でトラウマを体験すると、たとえ身体への物理的な影響や、悪夢やパニック発作などの症状が残ったとしても、その体験の記憶は失われてしまうということが明らかになっている。この考え方を、新石器時代の文化にとって正常、かつ自然だったと思われる自然との相互依存的な繋がりの知識を忘れてしまったという人間の健忘症に当てはめたならば、次の疑問が浮かぶ:この繋がりと調和の感覚を脅かした恐ろしい出来事は存在したのだろうか。
メツナーはそうした出来事の候補として、広範囲にわたる生命の損失や移住を余儀なくされることを伴う火山や地震災害、長期的な雨季や旱魃、急激な気候変動、略奪戦闘集団による侵攻などを挙げている。たとえば、中世ヨーロッパでのキリスト教による自然崇拝宗教への猛攻撃や、14世紀の人口の3分の1を壊滅させたペスト(黒死病)もトラウマを与える出来事だったと考えられる。
健忘のアナロジーは期待が持てるものだ、とメツナーは言う。なぜなら、全く新しいものへ適応していくことよりも、かつて知っていたものごとを思い出すことのほうが容易いからである。また、南北アメリカ、東南アジア、オーストラリアに住む先住民族は、彼らの生活様式の中で守り、維持してきたある種の不可欠な行為や価値 -〈文明化〉した人間が忘れてしまったもの- を、私たちに思い出させてくれる。
〈註〉
1. Metzner 1999, p.91 より引用
〈参考文献〉
Metzner, Ralph (1999). Green psychology: Transforming our relationship to the earth. Rochester, VT: Park Street Press.
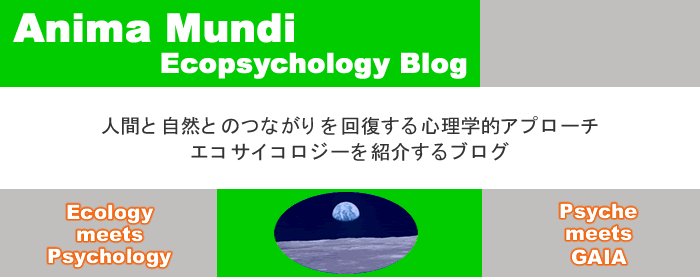

0 件のコメント:
コメントを投稿