人間-自然関係の精神病理 その1
人間-自然関係の精神病理 その2
人間-自然関係の精神病理 その3
人間-自然関係の精神病理 その4
人間-自然関係の精神病理 その5
人間-自然関係の精神病理 その6
人間-自然関係の精神病理 その7
エコロジカルな無意識の抑圧 (Repression of the Ecological Unconscious)
エコサイコロジーの提唱者セオドア・ローザック (Theodore Roszak) は、「工業社会に見られるなれあい的狂気は、エコロジカルな無意識の抑圧に深く根ざしている。エコロジカルな無意識との自由な行き来こそ、健全さへの道である」と述べている。1 ローザックによると、ユングの集合的無意識の概念は、後に全人類の宗教的象徴であるという点が強調されるようになったが、本来は前人類の動物や生態的元型 (archetype) を含むものであった。ローザックはその本来の意味を汲み、「宇宙進化の生きた記録」として、「エコロジカルな無意識(ecological unconscious)」と呼ぶことを提案している。
しかし、メツナーは「エコロジカルな無意識」という名称には異議を唱えている。私たちは「無意識」ではなく、「エコロジカルな意識(ecological consciousness)」を育成しようとしているため、その概念を「無意識」として具体化することは、その理解を無意識なままにしてしまうおそれがあるという。メツナーはより良い名称として、アルド・レオポルド (Aldo Leoplod) の「エコロジカルな良心 (ecological conscience)」を挙げている。「良心」という言葉には、道徳的価値や倫理的配慮を含意しているからである。
また、ローザックはフロイトのイド (id) を回復することを試みている。それはフロイト自身が考えた、色好みの捕食動物のようなものとしてのイドではなく、古代のエコロジカルな智慧の貯蔵庫として見るべきイドである。「生命圏の保存をめぐる地球の同盟者としてのイド。(そして)ガイアはイドという入り口から私たちのところへ手を伸ばしてくる」。2
しかし、メツナーはこの考えがローザックの試みを適えるものではないと考える。西洋の近代的な子育てによって、子どもが生まれながらに持つエコロジカルな感性の大部分が押し殺されているということは真実である。しかし、その一方、伝統的な社会におけるエコロジカルな知識や、自然への崇敬の念は両親や年長者から子どもへと受け継がれるものであり、そうした養成の過程なくして発現するものではないということも真実である。これこそ、伝統的文化の崩壊が環境の荒廃を招いているという理由のひとつである。古代の伝統が持つ儀礼行為の復興や、強力なエコロジカル・リテラシー(ecological literacy: 環境を読み取る能力)によって補われないかぎり、「エコロジカルな無意識との自由な行き来」が意味するものはなんであれ、健全さへの道には不十分である、とメツナーは述べている。
〈註〉
1. Roszak 1992 / 2001, p.320 木幡訳の日本語版を参照。
2. Roszak 1992 / 2001, p.291
〈参考文献〉
Metzner, Ralph (1999). Green psychology: Transforming our relationship to the earth. Rochester, VT: Park Street Press.
Roszak, Theodore (1992 / 2001). The voice of the earth: An Exploration of ecopsychology (2nd ed.). Grand Rapids, MI: Phanes Press.― 木幡和枝訳『地球が語る-宇宙・人間・自然論』(ダイヤモンド社,1994)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
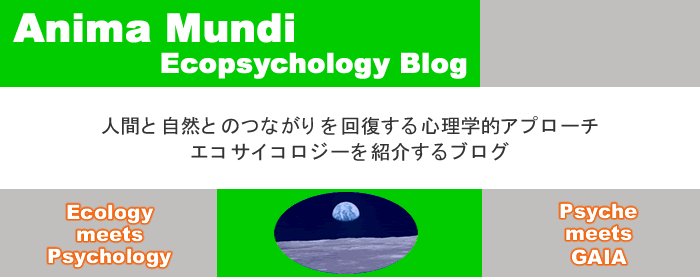

0 件のコメント:
コメントを投稿