1.心の核心はエコロジカルな無意識である。エコサイコロジーからすると、工業社会に見られるなれあい的狂気は、エコロジカルな無意識の抑圧に深く根ざしている。エコロジカルな無意識との自由な行き来こそ、健全さへの道である。
2.エコロジカルな無意識の中身は、ある程度、心性のなんらかのレベルにおいて、はるか昔の時間史の初期条件まで遡る、宇宙進化の生きた記録を象徴している。自然の秩序のある複雑性に関する現代の研究でわかることは、生命と意識はこの進化の物語から発したということであり、それらは、私たちが「宇宙」と呼んでいるさまざまな物理的、生物学的、精神的、文化的システムが順々に現れてくるなかで、自然システムの頂点を表している、ということだ。エコサイコロジーは、新しい宇宙論のこれらの発見を糧とし、それらを現実のものとして体験することを目指している。
3.無意識の抑圧された中身を回復させることが、まさしくこれまでの治療法の目標だったように、エコサイコロジーの目標もまた、エコロジカルな無意識に内在する、環境との本来的な相互依存感覚を目覚めさせることである。ほかの精神療法は人と人、個人と家族、個人と社会との疎外関係を癒すことを目指している。だが、エコサイコロジーは、人と自然環境との間に生じた、もっと根底的な疎外関係の治癒を目指している。
4.他の療法にとってもそうだが、エコサイコロジーにとっても、発達の決定的な段階は子どもの生活である。新生児の魔法を秘めたような世界に対する感覚においてこそ、あたかも天賦の才であるかのように、エコロジカルな無意識は再生してくる。機能的に「健全な」大人において、子どものもつ生得的なアニミズム的経験の質を回復することを、エコサイコロジーは目指している。そのために、エコサイコロジーは多くの知識をよりどころとするが、そこには原始的な生活をする人々の伝統的な癒しの手法、宗教や芸術に表れる自然神秘主義、野生の体験、ディープ・エコロジーがもたらす洞察などが含まれる。これらを適用して、エコロジカルな自我の創出という目標に資する。
5.エコロジカルな自我は、地球に対する倫理的責任感に向かって成熟をとげる。それは、他者に対する倫理的責任感として生き生きとした形で体験されるものである。エコサイコロジーは、この責任を織りあげて、社会的諸関係と政治諸決定という布地をつくりだす。
6.治療のプロジェクトのなかでも、エコサイコロジーにとってもっとも重要なのは、私たちの社会の政治権力の構造に浸透している、ある種の強制的な「男性的」性向の痕跡を洗いなおすことである。この性向は、自然を、あたかも自分たちとは別物の、なんの権利もない領域であるかのようにみなし、それを支配することを私たちにけしかける。その意味で、エコサイコロジーは、エコフェミニズムと「フェミニスト・スピリチュアリティ」運動が獲得した洞察のいくつか(すべてではなく)を、そうとう取り入れている。それにより、性的な類型という神話を打ち破ろうとするものである。
7.小さなスケールの社会的形態と、個人の権力の強化に資することはなんであれ、エコロジカルな自我の糧となる。大きなスケールの支配と、個人性の抑圧を目指すものはなんであれ、エコロジカルな自我を阻害する。したがってエコサイコロジーは、組織化のありようが資本主義的であれ集団主義あれ、現代のあらゆる巨大な都市的・工業的文化の本質的な意味での健全さに、深い疑問を呈する。だが、そうはいっても、人類の技術の才、また人類がこれまでに蓄積してきた、工業力に支えられた生命の拡張に役立つ手段を、すべて拒絶するわけではない。エコサイコロジーの社会的志向は、工業的なるものを超越することであり、それに敵対することではない。
8.地球の福祉と個人の福祉のあいだには、シナジー(相乗効果)をもつ作用関係がある、とエコサイコロジーでは考える。シナジーという言葉をあえて選んだ理由は、従来からこの言葉がもっている神学的な意味合いである。それはかつて、こう教えていた。人と神は救済を求めるなかで、協力という絆で結びついている、と。この言葉を現代の生態学で翻訳すれば、つぎのようになるだろう。地球が必要としていることは、人が必要としていることでもある。人の権利は、地球の権利でもある。1
〈註〉
1. Roszak 1992 / 2001, pp. 320-321. 木幡訳の日本語版を参照(pp.457-459)。訳者は「ecopsychology」を「生態学的心理学」、「ecological」を「生態学的」と訳しているが、筆者は 「エコサイコロジー」、「エコロジカルな」に変更している。
〈参考文献〉
Roszak, Theodore (1992 / 2001). The voice of the earth: An Exploration of ecopsychology (2nd ed.). Grand Rapids, MI: Phanes Press.― 木幡和枝訳『地球が語る-宇宙・人間・自然論』(ダイヤモンド社,1994)
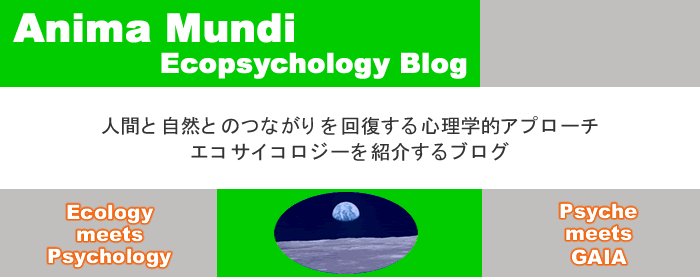

0 件のコメント:
コメントを投稿