人間-自然関係の精神病理 その2
発達の固着 (Developmental Fixation) :ポール・シェパードの見解
人間生態学者ポール・シェパード (Paul Shepard) は、著作『Nature and Madness』(1982)で、人間の心理と繰り返される環境破壊行為の相互作用について論じた最初のエコサイコロジストと言うべき人物である。シェパードは西洋文明(特にユダヤ・キリスト教文明)の文化的精神病理を発達遅延(arrested development)と分析し、彼が「個体発生的障害 (ontogenetic crippling)」と呼ぶものを経験しているのだという。人間の環境破壊行為はまさにこの個体発生的障害の表れである。
シェパードによる幼形成熟 (neoteny) と文化に提供される発達援助との相互作用の分析は特に興味深い。人間は成人に至るまでの未熟な期間や、養育者に依存する期間が他の生物と比べて長い、幼形成熟の生物種である。このため、文化によってに与えられる発達援助が不足したり、あるいは全くないような場合には破滅的な結果を招く。1 シェパードは旧石器時代の狩猟採集社会を生態学的にバランスのとれた生活様式のモデルとして挙げ、およそ1万2千年前の農耕社会の始まりによって、人間は何万年もの間健全に機能してきた発達の手段を失いだした、または誤用しだしたのだという。
太古の発達様式が慢性的に不完全になりつつあると考えられるのは、幼児-養育者関係と青年期の通過儀礼の2つの段階である。シェパードによると、農耕畜産型社会が発達途上にある子どもと世界自然との間の距離を深め、それによって、完全に成熟した大人へと向かう重大な過程の中で直面する数々の問題に向き合うことを困難にしてしまった。
エリクソン (Erick Erikson) の発達モデルでは、青年期は子どもが「自己同一性と自己同一性拡散」の対立に巻き込まれる時期である。エリクソンによると、この段階の混乱をうまく乗り越えられない若者は、「極端に排他的で不寛容であり、肌の色や文化的背景が〈異なった〉他者を排除することにおいて非情」になりやすい傾向があるという。2 家族という母体からより大きな社会への過渡期を乗り越えるための手本となる体系を提供することは、伝統的社会にみられる通過儀礼が果たしてきた役割であった。現代においてこのような青年期の通過儀礼が急激に価値を失い、減少しているのは明らかである。今も残る成人男子の通過儀礼は軍の入隊式や、大学のフラタニティ(社交クラブ)入会のしごき、若いストリートギャングの仲間内での無益な儀式にのみ見受けられる。
またシェパードは、青年期の通過儀礼の喪失に加えて、幼児と養育者との絆が形成される最初期の段階が中断されたり、妨げられたりした場合に発現する「調和異常」(unity pathology) と彼が呼ぶものについても指摘する。エリクソンの発達モデルによると、この段階は子どもの発達途上にある自己感が「基本的信頼と不信の対立」の問題に対処する時期である。この段階をうまく乗り越えられなかったならば、よくても慢性的な不安感をもつことになるか、最悪の場合、猜疑心をもち、妄想型の精神疾患による暴力へと向かう傾向もみられる。リードロフ (Jean Liedloff) によるアマゾンインディアンの母親と幼児の絆の研究と「連続性の概念 (continuum concept)」は、狩猟採取社会にみられる熱心な早期愛着関係が長期に渡る依存性を引き起こすのではなく、神経組織をよりよく機能させるというシェパードの主張を支えるものになる。
シェパードは個体発生的障害説を次のようにまとめている。「人間はいまや世界中で最も薄弱な自己同一性構造を持つものかもしれない。旧石器時代の基準でいえば、幼稚な大人だ」。3 この集団的狂気が招くひどい結果のひとつは「私たちが漠然と期待を裏切られていると感じる自然の世界にいつでも歯向かおうとしていること」である。一方、自然の世界や社会が自分たちに必要なものを与えてくれるという基本的信頼を幼年期に築いた若者は、競争優位を得るための絶え間ない苦闘を要求する世界観に魅了されりはしないだろう。
この集団的発達遅延への可能性ある治療法について、シェパードは多くを述べていない。しかしメツナーは、立派な年長者によって執り行われる通過儀礼を再び慣習化することや、幼少期の絆の脆さに対してもっと繊細な感性をもつことが、この病状を好転させるために必要になるだろうと言う。シェパードいわく:
自己と世界が生態学的に調和している感覚は…私たちみんなが受け継いできたものである。それは生物の中に、ゲノム(遺伝情報)と初期の経験との相互作用の中に潜在している。そうした初期の経験、漸成の過程は、人間と人間以外のものとが健全に交感しあっていた進化上の過去の遺産である。4
〈註〉
1.前回紹介した「人間優越コンプレックス」の形成に大きな関連性があると思われる。
2.Erikson 1980, p.97
3.Shepard 1982, p.124
4.Shepard 1982, p.128
〈参考文献〉
Erikson, Erik (1959 / 1980). Identity and the life cycle. New York: Norton & Co.
Liedloff, Jean (1977). The continuum concept. Reading, Mass.:Addison-Wesley.-山下公子訳『野生の旅:いのちの連続性を求めて』(新曜社,1984)
Metzner, Ralph (1999). Green psychology: Transforming our relationship to the earth. Rochester, VT: Park Street Press.
Shepard, Paul (1982). Nature and madness. San Francisco: Sierra Club Books.
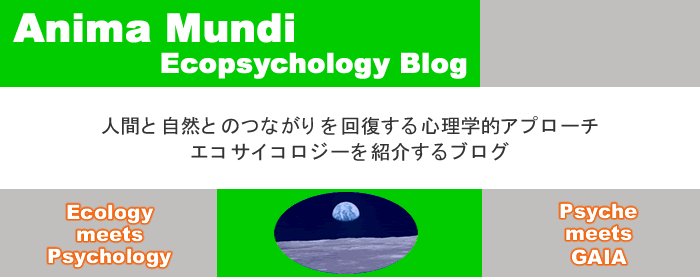

0 件のコメント:
コメントを投稿