人間-自然関係の精神病理 その1
人間-自然関係の精神病理 その2
人間-自然関係の精神病理 その3
人間-自然関係の精神病理 その4
人間-自然関係の精神病理 その5
ナルシシズム (Narcissism)
地球規模で展開される生態系破壊の原動力となっているもののひとつに、特に極度に工業化・近代化した社会における過剰消費の問題が挙げられる。消費主義 ―より多くの人々がより多くのモノを欲しがり、購入する― は、前回紹介した、個人レベルにおける強迫行為・嗜癖メタファーの集合的な表れとして見ることができる。消費は広告宣伝によって、大規模、且つ、人為的に極端なレベルまで推し進められているが、そこには私たちの心の中に潜むナルシシズム(自己愛)が大きなな役割を担っていると示唆する多くの証拠が存在する。ナルシシズムとは、膨張した誇大な自己イメージや、深層にある無価値感や空虚さを覆い隠すため特権意識を持つことなどを特徴とする人格障害である。
心理学者のクッシュマン (Philip Cushman) は、ナルシシズムと消費文化の明白な類似性を引き出している。より高価でより技術的に進歩した消費財を絶え間なく追い求めることは、「偽りの自己 (false self)」を満足させる。安定のない、空虚な内なる本当の自己は不安にさらされ、傷を負ったままであるのに、偽りの自己はモノを買うことで内なる空虚さを埋めようとすることを駆り立てる。クッシュマンが言うように、「空虚な自己は、ますます大きくなる疎外と戦うために、モノ、カロリー、経験、政治家、恋愛のパートナー、共感してくれるセラピストを消費することによって、絶えず満たされる経験を求める」1。
エコサイコロジストのカナー (Allen Kanner) とゴメス (Mary Gomes) は、こうした一連の研究の幅を広げ、もしアメリカ文化が集団ナルシシズムに陥っているという診断が正しいならば、それは環境保護論者にとって困難な課題になると言う。平均的な消費者は心の中で不十分さを感じ、その無価値さを癒すため、もっと浪費させようと企む嵐のような広告の爆撃を絶えず受け続ける。したがって、環境保護論者が物質消費をもっと減らそうと嘆願しても、権利主張や恐れによって聞こえなくなった消費者の耳には届かないかもしれない。「過剰な物質主義だと彼ら(消費者)を非難すれば、環境に関した彼らの習慣を大幅に変えることになるよりも、むしろそうした忠告が、主として彼らの全体的な挫折感を増幅させるおそれがある」。2
〈註〉
1.Kanner and Gomes 1995, p.79より引用
2.Kanner and Gomes 1995, p.89
〈参考文献〉
Kanner, Allen and Gomes, Mary (1995). The all-consuming self. In T. Roszak, M. Gomes, and A. Kanner (Eds.), Ecopsychology: Restoring the earth, healing the mind (pp.77-91). San Francisco: Sierra Club Books.
Metzner, Ralph (1999). Green psychology: Transforming our relationship to the earth. Rochester, VT: Park Street Press.
登録:
コメントの投稿 (Atom)
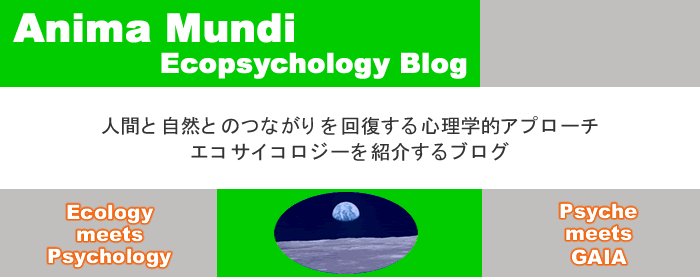

0 件のコメント:
コメントを投稿