人間-自然関係の精神病理 その1
人間-自然関係の精神病理 その2
人間-自然関係の精神病理 その3
人間-自然関係の精神病理 その4
人間-自然関係の精神病理 その5
人間-自然関係の精神病理 その6
人間-自然関係の精神病理 その7
人間-自然関係の精神病理 その8
解離 (dissociation) (1)
メツナーが最後に挙げる診断メタファーは解離 (dissociation) である。無意識の創造の抑圧を重要視するフロイト派や後フロイト派の考えとは対照的に、近年、解離の概念への関心が復活してきている。心的外傷後ストレス障害(PTSD: post-traumatic stress disorder) や多重人格障害(MPD: multiple personality disorder) 1 のような解離性障害の診断が頻繁になされるようになっている。解離は、実際、ごく普通の自然な認知機能である。何かに意識を集中させるという単純な行為にも、注意を向けていないものへの認識を排除する、ある程度の解離が含まれている。また解離は、外的世界の知覚を遮断し、内なるイメージ、記憶、印象に注意を向ける、催眠やトランス状態の際に役割を果たす。
フロイト派の見解では、抑圧された無意識(イド)に内在する精神的要素(思考、イメージ、感情など)は「快楽原則」に従って機能する、まとまりを欠いた、原始的で、幼稚なものである。一方、顕在意識(ego) は「現実原則」に従って機能し、合理的にまとまりのあるかたちで、現実の要求に順応することができるものである。ジャネ(Pierre Janet) やヒルガード(Ernest Hilgard) らのような分離説派の見解によると、解離とは、等しくまとめられた合理的かつ現実とつながりのある意識の織りなす束が〈縦〉に分割したものだという。例えば、痛切な体験における精神的、感情的要素は解離することがあり、その結果、何を見て何を思ったかは覚えていても、何を感じたかは覚えていない。逆に、ある種の刺激によってパニックの感情が引き起こされることがあっても、起こった出来事の認知的記憶は解離し続けている、ということがある。
解離性障害の中で最も極端な形である多重人格障害は、「自我状態」や「分身」と呼ばれる2つ以上の同一性が形成されるものである。多重人格者は、自分自身と別の名前や別の人格特性との連続性を維持する。ヒルガードが言うように、「隠れた(あるいは解離した)人格は、時に表に出た人格よりも正常で、精神的にも健全である。これは、1次過程の思考によって大きく統制された原始的な無意識であるという考えよりも、正常な意識の分裂という考えのほうがうまく一致する」。2
「エコロジカルな無意識」の抑圧という考えよりも、この解離や分裂の概念のほうが、環境に関する人間の集団的病理のより正確で、より有効な理解を与えてくれる、とメツナーは言う。西洋の工業社会の文化全体が、そのエコロジカルな基層から解離している。それは、地球の複雑性や相互依存の繊細な網の目に関する知識や理解が、私たちの心の忘れさられた基底に漠然と不完全なかたちで留まっているということではない。私たちは環境に与える影響に関しての知識を持っているし、土地、水、大気の汚染や荒廃を認識することもできる。しかし、私たちはそのことに対して注意を払っていないし、持っている知識を体験と結びつけていない。もっと正確に言えば、私たちが関与する政治、経済、教育の制度すべてにこの解離が組み込まれているため、人は自然世界に対して適切に対応できないと感じている。
〈註〉
1.DSM-Ⅳからは、「解離性同一性障害(DID: Dissociative Identity Disorder)」と名称変更されている。
2.Metzner 1999, pp.94-95 より引用
登録:
コメントの投稿 (Atom)
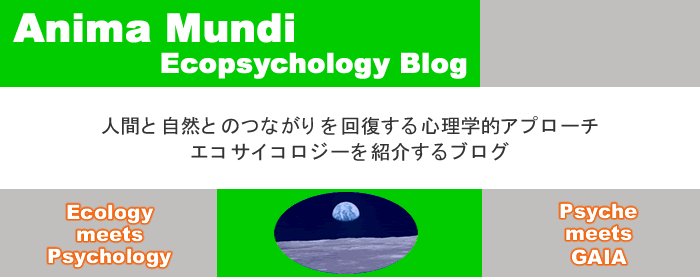

0 件のコメント:
コメントを投稿