人間-自然関係の精神病理 その1
人間-自然関係の精神病理 その2
人間-自然関係の精神病理 その3
人間-自然関係の精神病理 その4
人間-自然関係の精神病理 その5
人間-自然関係の精神病理 その6
人間-自然関係の精神病理 その7
人間-自然関係の精神病理 その8
人間―自然関係の精神病理 その9
解離 (dissociation) (2)
西洋の心理における人間と自然との解離的分裂は、霊性的なもの(spiritual) と自然的なもの (natural) との分裂と深く関わりがある。それはまるで私たちが2つの自己を持っているかのようである。ひとつは霊性的な自己で、高次の領域へと上昇するものとして考えられている。もうひとつは、肉体感覚や感情を含む自然的な自己で、それは私たちを下降させるものである。こうした2元的な価値を含んだ観念のため、霊性的(人間的)なものは常に自然的(動物的)なものよりも優れているとみなされる。3
また、こうした分裂だけでなく、これら2つの領域や傾向が対立することもある。救済や悟りを得るため、霊性的なものになるには、自らの〈下級〉な動物的本能や理性のない感情を克服し、肉体的なエゴを征服しなければならない、ということを宗教は説いてきた。主に自然に従い、模倣することを基本とする錬金術の伝統では、この種の特別な霊性的作業を「自然に反する作業 (the opus contra naturam) と呼んでいた。
人間の霊性的価値と自然の実態、肉体、感覚との解離的分裂は、宗教的世界観の崩壊を生き残り、フロイトの精神分析における純粋な心理的パターンとして再び登場することになる。この場合は、主に人間の意識である自我 (ego) と、身体に基づいた動物的本能や衝動であるイド (id) の対立である。自我は意識を獲得して真の人間になるために、イドと闘わなくてはならない。文化の集合的レベルでは、この自然との対立した関係が「文化への不満 (Das Unbehagen in der Kultur)」 ―これは、私たちが文明の可能性のために払わざるをえなかった不可避の犠牲であった― をもたらした、とフロイトは考えた。
西洋人の自己概念におけるこの解離的分裂が、生態学的に悲惨な結果を招いたことは明白である。私たちが精神的にも霊性的にも自らの自然 ―身体、本能、感情など― から切り離されていると感じるならば、その分離は外部へとも投影される。その結果、私たちは自分自身が大いなる自然の世界や地球から切り離されていると感じるのである。霊性的に向上するため、または真の人間になるために、私たちが自分の身体の自然な感情や衝動と闘い、抑制し、統制する必要があると信じるのならば、これと同じような対立と制御の課題も外部へと投影されて、西洋の「自然の征服」というイデオロギーを支持するものになる。
この歪んだイメージは、次のような事実に反するものである。私たち人間は、実際に、自然から切り離された存在ではないし、自然よりも優れた存在ではない。また、自然を支配する権利、日々の糧に必要なものを超えて利用する権利を持たない。私たちは地球の一部である ―私たちは地球上に住んでいるのではなく、地球に住んでいる。私たちは地球という巨大な生命体の体内の細胞である。もし、ある細胞集団が体内の他のエネルギーシステムを支配し、解体しようとするならば、生命体は健全に機能し続けることができなくなる。
霊性的なものと自然的なものが対立するという考えや、霊性はつねに自然を超越しなければならないという考えは、多神教や伝統的なアニミズム社会には共有されていない、文化的な相対概念である。世界中の先住民文化では、自然世界は精霊の領域であり、聖なるものとみなされている。つまり、自然的なものは霊性的なものと考えられている。この信念から、自然を敬う姿勢、バランスのとれた関係を維持しようとする願望、未来の世代や生態系の未来の健康 ―つまり、持続可能性― を考慮することの必要性への直感的理解が追随してくるのである。自分たちとは異なる世界観を理解し敬うことは、霊性と自然との解離に執着する西洋にとって最適な解毒剤となるかもしれない。
〈註〉
3.「その2」でレビューした、人間優越コンプレックスと大いに関係がある。
〈参考文献〉
Metzner, Ralph (1999). Green psychology: Transforming our relationship to the earth. Rochester, VT: Park Street Press.
登録:
コメントの投稿 (Atom)
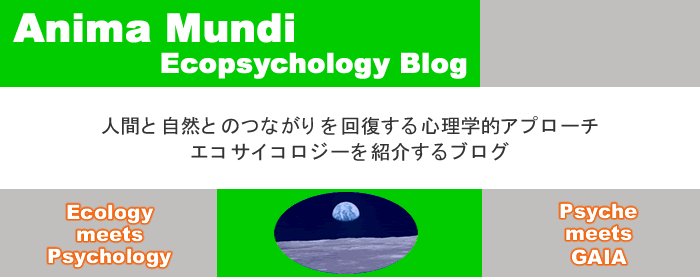

0 件のコメント:
コメントを投稿